「照明がつかない」「スイッチを押しても反応しない」──そんなトラブル、経験ありませんか?
電気の仕組みは目に見えないだけに、どこが悪いのか分からず不安になりますよね。
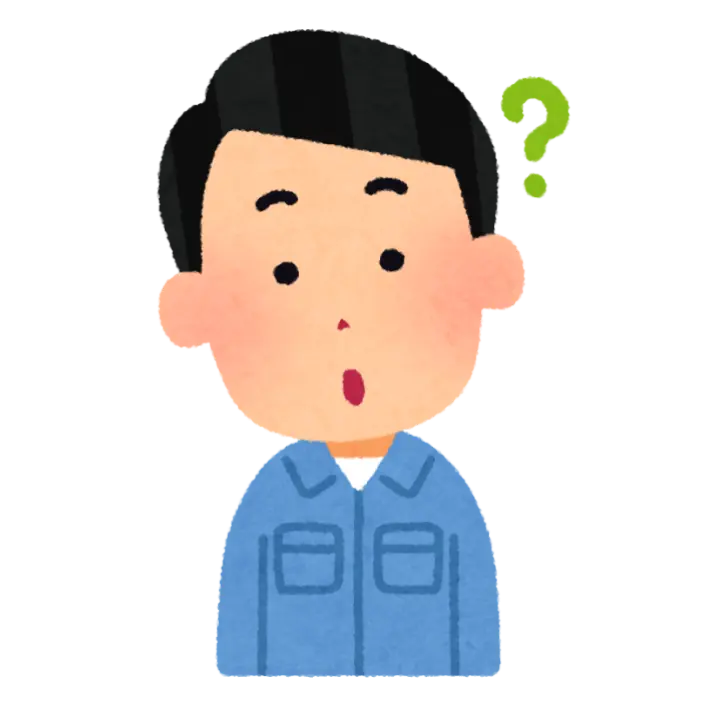
電気って、“部品の寿命”なんてあるんですか? 見た目は変わらないのに突然壊れたりして…

あるよ。しかも壊れ方にはちゃんと“サイン”がある。焦げ臭い、動かない、反応が鈍い——こうした症状を見れば、どの部品が原因かおおよそわかるんだ。
この記事では、現場経験をもとに
- 故障の兆候をどう見抜くか
- 寿命の目安
- 初心者でも安全にできる点検・交換方法
をわかりやすく解説します。
電気のトラブルを「怖い」から「理解できる」に変えていきましょう。
✅電気部品の寿命と劣化の兆候
✅故障のサインの見分け方
✅よくある故障パターンと応急処置
⚠ 安全上の注意喚起(必ずお読みください)
電気部品の故障は、単なる「動かない」「点かない」といった不具合にとどまらず、
誤動作や通電異常による感電・火災・機械損傷・人身事故・死傷につながる危険があります。
応急処置や原因調査を行う際は、必ず以下の点を徹底してください。
🔒1. 電源の完全遮断
🧤 2. 感電防止対策の徹底
🚧 3. 作業エリアの安全確保
🛑 4. 応急処置に関する重要注意
🛑【最重要】安全が確保できない場合は、直ちに作業を中止してください。
🛠応急処置に関する重要注意
安全性の保証なし
応急処置による回復は一時的なものです。安全が完全に保証された状態ではありません。二次トラブルの危険性
根本原因を特定・解決せずに装置を再稼働させると、短絡(ショート)・焼損・機械破損など、より深刻な二次トラブルを引き起こす可能性があります。根本対処の原則
基本は新品交換です。
新品交換が困難な場合は、装置全体の一時停止を検討してください。
部品の再利用や分解修理は、安全性とメーカー保証の両面でリスクが高いため、原則として推奨しません。
📝免責事項
本記事でご紹介する内容は、参考事例の紹介を目的としており、特定の状況に対する動作や安全性を保証するものではありません。
実際の作業は、自己責任において行ってください。
本記事の内容に基づいて実施された作業により、いかなる損害(直接・間接を問わず)が生じた場合においても、著者および掲載元は一切の責任を負いかねます。
電気部品にも「寿命」はある
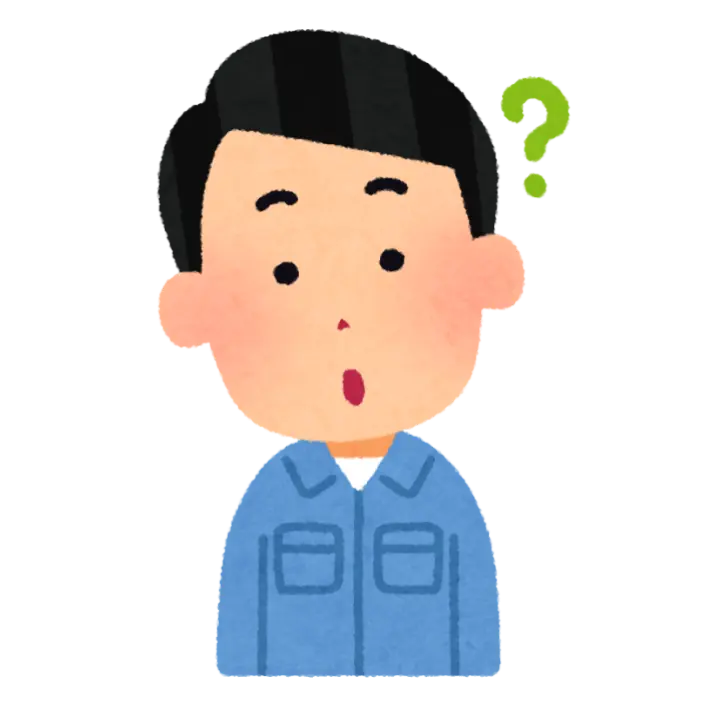
スイッチとか操作ボタンとかって、何年も使えるイメージなんですが、ほんとに寿命ってあるんですか?

もちろんあるよ。金属部分の酸化や接点の摩耗、絶縁材の劣化などで性能は少しずつ落ちていく。
見た目が無事でも、“通電しづらくなる”ってことはよくあるんだ。
電気部品の寿命=“劣化による通電不良”
電気部品は消耗品。
スイッチ・照明・センサー、ボタンなどは、通電の繰り返しによって内部が摩耗・劣化し、やがて正常に電気が流れなくなります。
たとえば、スイッチを何度も押さないと機械が動かなかったり、
照明が「一瞬ついてすぐ消える」といった症状が現れたら、それは寿命のサインです。

「通電しても反応しない」=電源が悪いとは限らない。
部品内部の抵抗が大きくなって、電流が流れにくくなっている場合もある。
この考え方、オームの法則に通じるんだよ。
故障のサインを見逃さないために
電気部品の故障は、いきなり壊れるよりも「小さなサイン」から始まることが多いです。
そのサインを見逃さず、早めに気づける人ほど未然にトラブルを防げます。

この装置、たまにボタン押しても反応しないんですけど…でも動くときもあるんですよね。

それ、もう“故障のサイン”が出てるかもしれませんね。完全に壊れる前に少しずつ異常が出るんです

え、でも動くときもあるのに?

“動くときもある”が一番危険なんです。接触不良とか抵抗の増加で、条件が合った時だけ通電してる可能性があります。現場で多いのは、「動くときもある」「反応が鈍い」「少し焦げ臭い」などの軽い異変です。
これらは内部の抵抗値上昇や接点の酸化、コイルの劣化など、
部品の性能が徐々に低下しているサインです。
たとえば…
- スイッチを押してもたまに反応しない → 接触不良
- 電源を入れるときにワンテンポ遅れる → パワーサプライの出力低下
- センサーが誤検出する → 光学素子の汚れ or 出力回路の劣化
実際に有ったケースでは、制御盤内の押しボタンを強く押さないと反応しないという相談がありました。
調べてみると、押しボタンの接触抵抗が大きくなっていたのが原因で反応が鈍くなっている状態ででした。
つまり、ボタン自体は「動作しているように見える」けれど、押下時に接点部分で接触不良が起きて信号が正しく伝わっていなかったのです。
つまり、“動くけど調子が悪い”は、もう壊れかけの状態ということ。
実体験ベース:電気部品の故障パターン6選
パワーサプライの出力不良

操作パネルの表示が出ません。ブレーカーは確実に入っているんですが…

なるほど、よくあるケースだね。パワーサプライの出力が弱っているか、止まっている可能性があるよ。外見はなんともなくても、中で電圧が下がっていることがあるんだ。
装置に必要な直流の電気(電圧)を作り出す「電源装置」です。これが故障すると、装置全体に電力が供給されず、動作しなくなります。
① 故障のサイン
制御盤や基板の「電源ランプ」や「LED」が点灯しない
リレーやセンサーが一切反応しない
表示パネルが「一瞬だけ点灯して、すぐに消える」
② 原因の確認・確定方法
ここでは、自分でできる確認と、専門家に任せる確認を分けて考えましょう。
✅ 初心者でもできる確認
見た目の確認: パワーサプライユニットに焦げ跡や変色、膨らみがないか。
異臭・ほこりのチェック: 焦げ臭いニオイや、ほこりの大量付着がないか。
⚠ 専門作業(プロ向け)
テスターで電圧を測定: 入力電圧が正常なのに、出力電圧が規定値より低い、または0Vの場合は、パワーサプライ本体の不良です。

(筆者撮影)パワーサプライ出力不良の様子
主な原因
長期間の使用による「電解コンデンサ」という部品の劣化が最も一般的です。これにより、電圧を安定して保つことができなくなります。
パワーサプライが機械や基板に送り出す電気の圧力(電圧)です。これが足りないと、機器は正常に動けません。取扱説明書などで規定の数値を確認しましょう。
電気を一時的に蓄え、放出する「バッテリーのような部品」です。内部的に電解液が入っており、長期間使用するとこれが乾燥し、性能が劣化します。パワーサプライの故障原因で最も多い部品の一つです。
③ 対処法・応急処置
応急処置
電源を切り、ほこりがあればエアダスターで軽く清掃します。根本解決にはなりませんが、ほこりによる放熱不良が一因の場合、一時的に改善する可能性があります。根本対処
部品内部の部分修理はせず、ユニットごと新品交換が基本かつ最も安全です。再発防止
突発的な停止を防ぐため、5~7年を目安に予防交換することをおすすめします。

一瞬だけ表示がつくのは、もう寿命ってことですか?

まさにそれ。中のコンデンサが限界で、最後のあがきをしている状態だよ。このまま使い続けると、ある日を境に完全に停止するから、サインを見逃さないことが大事だね。
「動いたり止まったり」は危険信号 → 交換のサインです。
出力電圧の低下は寿命の合図 → 早期発見が大事。
だましだまし使わない → 予防交換で大きなトラブルを防ぎましょう。
マイクロスイッチのONパンク(ショートモード)

押してもいないのに機械が動くんです。スイッチが勝手にONになってるみたいで……

なるほど、それ“マイクロスイッチのONパンク”かもしれませんね。スイッチ内部の接点が溶けてくっつき、常に通電したままになっている状態です。
① 故障のサイン
スイッチを押していないのに、機械が動作する
動作を示す「ランプ」が消えずに点きっぱなし
スイッチをOFFにしても、動作が止まらない
スイッチ内部の接点が熱で溶けて接着し、物理的に切り離せなくなった状態です。見た目は普通でも、内部では常に電気が流れ続けている、危険な故障です。
② 原因の確認・確定方法
✅ 初心者でもできる確認
外観点検: スイッチの樹脂部分に焦げ跡や変色、変形がないかを確認する。
手触り確認: スイッチを押した時に、本来の「カチッ」というクリック感や戻りがあるか。
⚠ 専門作業(プロ向け)
テスターによる導通チェック: スイッチを押していない状態(OFF)でテスターを当て、導通(ピッという音)があればONパンクと確定します。
主な原因
スイッチが切りたい電流(特にモーターなどによる大きな電流)に対して能力不足の場合、大きな火花(スパーク)が発生し、接点を溶かして固着させます。
電気の通り道がつながっているかどうかを調べること。テスターで導通モードに設定し、スイッチがOFFの時に「ピッ」と音が鳴れば、異常(ショート)です。
③ 対処法・応急処置
応急処置
※安全が第一条件です
機械を完全に停止させた上で、該当スイッチへの配線を外し、誤動作を防止します。これにより一時的に安全を確保できます。根本対処
内部は修理できません。マイクロスイッチ自体の新品交換が唯一の解決策です。再発防止
スイッチの定格電流(扱える電流の値)に余裕を持たせて選定する。
大きな電流が流れる回路では、リレーと呼ばれる部品を間に挟み、スイッチには小さな電流だけを流す構成に変更する。

スイッチって、見た目は普通でも中で貼りつくんですね。

そう。特に能力以上の電気を切らせていると、中で火花が散って、いずれ溶接されたようになるんだ。『スイッチを切っても動き続ける』のは危険信号だから、すぐに対処しよう。
「OFFにできない」は重大な故障 → 機械が暴走する危険があります。
原因は接点の溶着 → スイッチの能力超えや火花が原因です。
新品交換と回路の見直し → 交換だけでなく、再発防止策の実施が必須です。
押しボタンの接触不良(反応が不安定)

ボタン押しても反応したりしなかったりするんですよ。何回か押すと動くんですけど…

それ、“接触不良”の典型ですね。中の接点が汚れたり酸化したりして、電気がちゃんと流れたり流れなかったりしてるんです。
① 故障のサイン
ボタンを押しても反応が不安定(動いたり動かなかったり)
強く押さないと反応しない
押した時の感触が重い、または戻りが遅い
「カチッ」という音が鈍い、または鳴らない
② 原因の確認・確定方法
✅ 初心者でもできる確認
外観の確認: ボタンの周りにホコリ、油、水分などの汚れが付着していないか。
押し心地チェック: 電源OFFで「カチッ」というクリック感と、すっと戻る感触があるか。
⚠ 専門作業(プロ向け)
テスターで導通チェック: ボタンを押した状態でテスターの導通音が不安定(鳴ったり鳴らなかったり)、または抵抗値が大きくバラつく場合は接触不良と確定します。
主な原因
接点の酸化(空気中の酸素や湿気によるサビ)や、ホコリ・油などの汚れの付着です。内部のバネの疲れや摩耗も原因になります。
電気が接点を通るときの通りにくさを表します。これが大きくなると、ボタンを押しても電気が十分に流れず、機器が反応しなくなります。
③ 対処法・応急処置
応急処置
※必ず電源OFFで行ってください
接点復活剤を噴射する、またはエアダスターで内部のホコリを吹き飛ばすことで、一時的に改善する可能性があります。根本対処
内部の摩耗や酸化は元に戻せません。ボタンスイッチの新品交換が最も確実な解決方法です。再発防止
湿気や粉塵が多い場所では、防水・防塵仕様(IP規格) のボタンを選定する。
定期的な点検計画に操作部品のチェックを組み込む。

押すたびに反応が違うのって、意外と危ないんですね…。

そうなんだ。“動くときもある”が一番たちが悪い。完全に止まれば交換するけど、まだ動くからと放置すると、ある日突然、全く反応しなくなるからね。
「反応が不安定」は交換のサイン → だましだまし使わない。
原因は接点の汚れや摩耗 → 清掃は一時しのぎに過ぎない。
基本は交換、環境に合った部品で予防 → 再発防止が大事。
光電センサー(光電管装置)の出力不良・ONパンク(ショートモード)

センサーの前に何もないのに、機械が止まっちゃうんです。まるで“見えない何か”を検出してるみたいで…

それ、“ONパンク”の可能性がありますね。センサー内部の出力回路が壊れて、常にONの信号を出し続けている状態かもしれません。
① 故障のサイン
検出物がないのに、センサーの「動作表示ランプ」が点きっぱなし
機械が意図せずに停止し続ける(または動き続ける)
光を遮断しても、センサーの反応が全く変わらない
センサー表面のレンズに、汚れや損傷がある
② 原因の確認・確定方法
✅ 初心者でもできる確認
外観チェック: レンズにホコリや油などが付着して光を遮っていないか。物理的な損傷はないか。
遮光テスト: センサーの電源を入れた状態で、手や紙で光路を完全に遮断しても、動作ランプが消えるかどうかを確認する。
⚠ 専門作業(プロ向け)
テスターで出力電圧を測定: 検出物がない状態(OFFになるべき時)で、出力端子間の電圧を測る。電圧が出続けていればONパンクと確定します。
主な原因
出力部への過剰な電流や、経年劣化による半導体の破壊が主原因です。雷サージなどの異常電圧がきっかけになることもあります。
センサー内部の出力を担当する半導体(トランジスタ)が壊れ、電気のスイッチが“切れない”状態になることです。センサーとしては“常に検出中”という誤った信号を出し続けます。
③ 対処法・応急処置
応急処置
※システム全体を安全に停止させてから
誤動作を防ぐため、該当センサーの出力配線を一時的に外します。これにより機械の誤動作は止まりますが、その機能は失われます。根本対処
内部の電子回路は修理不能です。センサーユニット全体の新品交換が唯一の解決策です。再発防止
一般的な寿命目安である5~7年を参考に、予防交換を検討する。
過酷な環境では、防塵・防滴仕様のセンサーを選定する。
雷が心配な地域では、サージ保護素子の追加を検討する。

センサーって、外から見ると壊れてるかわからないんですね…

そう。光はちゃんと出ていて、一見正常に見えるから厄介なんだ。でも中身の“信号を切るスイッチ”が壊れているから、ずっとONのままなんだよ。定期点検で早期に見つけないと、ラインが停止する大きなトラブルになる。
「何もないのに反応する」は故障のサイン → 内部が壊れています。
原因は出力部のショート → 修理はできないので交換必須。
予防交換と環境対策で安定稼働 → 定期点検で突然死を防ぎましょう。
リレー・接触器のマグネットコイル引き不良

いつも“カチッ”って音がする接触器が、今日は無反応なんです。電気は来てるのに…

それ、“マグネットコイルの引き不良”かもしれません。コイルが劣化して電磁力が弱まり、スイッチを引き込む力が足りなくなっている状態ですね。
① 故障のサイン
動作時に「カチッ」という音がしない、または極端に小さい
一瞬だけ動くが、すぐに元に戻ってしまう
リレーや接触器のコイル部分が異常に熱い、または焦げ臭い
手で強く押し込むとなんとか動作する
② 原因の確認・確定方法
✅ 初心者でもできる確認
外観・嗅覚チェック: コイル部分に変色や膨らみ、焦げ跡がないか。焦げ臭いニオイがしないか。
音の確認: 動作時の「カチッ」という音が、以前と比べて弱く・鈍くなっていないか。
⚠ 専門作業(プロ向け)
- テスターでコイル電圧測定:コイルの定格電圧が出ているのに動作しない場合はリレー・接触器の不良
テスターでコイル抵抗を測定(測定は電源を遮断して): 規定の抵抗値から大きく外れている(無限大または極端に低い)場合は、コイルの断線またはショート(短絡)と判断できます。
主な原因
コイルの経年劣化(断線)、過電圧による絶縁劣化(ショート)、またはコイルへ供給される電圧の低下が挙げられます。
リレーや接触器内部にある電磁石のコイル(巻き線)です。ここに電気が流れることで磁力が発生し、機械的なスイッチ(接点)を「カチッ」と引き込み、回路のON/OFFを切り替えます。
③ 対処法・応急処置
応急処置
※危険を伴うため基本的には非推奨
機械を完全に停止させ、該当リレー/接触器によって制御される回路の動作を一時的に止めます。叩いたり無理に押し込むと、さらに状態を悪化させるため絶対に避けてください。根本対処
コイルの劣化は回復できません。リレーまたは接触器ユニット全体の新品交換が唯一の安全確実な方法です。再発防止
コイルの定格電圧(AC/DCや電圧値)を厳守する。
一般的な寿命目安である5年程度を参考に、予防交換を計画に組み入れる。
制御電源系統に異常(電圧変動など)がないかを定期的に確認する。

「音が小さい」くらいで交換って、ちょっと早い気もしますが…

その“音が小さい”が、力尽きる前の最後のサインなんです。完全に動かなくなる前に交換すれば、計画停止で済みます。動かなくなるその日まで待つと、ラインが突然止まる大きなトラブルになりますよ。
「カチッと鳴らない」は動作不良の第一歩 → コイルの力を疑おう。
コイルの抵抗測定で健康状態がわかる → 断線・ショートは交換必須。
予防交換で突然死を防ぐ → 音や動作のわずかな変化を見逃さない。
⑥ 換気ファンの動作不良

換気ファンが回らなくて…。でも、電源は入ってるみたいなんです。

よくあるね。ファンは“動く=電気が流れてる”と思われがちだけど、実は機械的にも電気的にも原因が隠れてるんだ。
① 故障のサイン
電源を入れてもまったく回転しない
回転が遅く、風量が弱い
ブーンという音だけで回らない
回転時にカラカラ、ゴリゴリという異音や振動がする
焦げ臭いニオイや、モーター部分が異常に熱い
② 原因の確認・確定方法
✅ 初心者でもできる確認
外観・嗅覚チェック: ファン内部にほこりの塊や異物が詰まっていないか。焦げ跡や変色、焦げ臭いニオイがないか。
手動回転チェック(電源OFFで!): ファンブレード(羽根)を手で軽く回し、スムーズに回転するか、重さや引っかかりがないかを確認する。
⚠ 専門作業(プロ向け)
テスターで電源電圧確認: モーターへの入力端子に規定の電圧が来ているか測定する。
主な原因
機械的にはベアリング(軸受け)の摩耗や固着、異物の詰まり。電気的にはコンデンサの劣化やモーターコイルの断線・焼損です。
単相モーターのファンに使われる部品で、モーターに回転を始めさせるための「押し出す力(トルク)」を生み出す役割があります。これが劣化すると、モーターはブーンと音を出すだけで回らなくなります。
③ 対処法・応急処置
応急処置
※安全が最優先です
電源を切り、ファンブレードや吸気口に詰まったほこりや異物を取り除きます。これだけで回り始めることがあります。どうしても回転が復帰しない場合は電源から切り離して端子を絶縁処置して下さい。モーターが発熱して焼損などに至る場合も有ります。根本対処
ファンの新品交換する。
再発防止
定期的な清掃: ファンブレードとフィルターの目詰まりを防ぎ、モーター負荷を軽減する。
- 予防交換: 連続運転のファンは、5年を目安に状態を点検・交換することを検討する。
電気が流れる危険な部分を、絶縁物(電気を通さないもの)で覆い、感電・短絡を防ぐための処置。
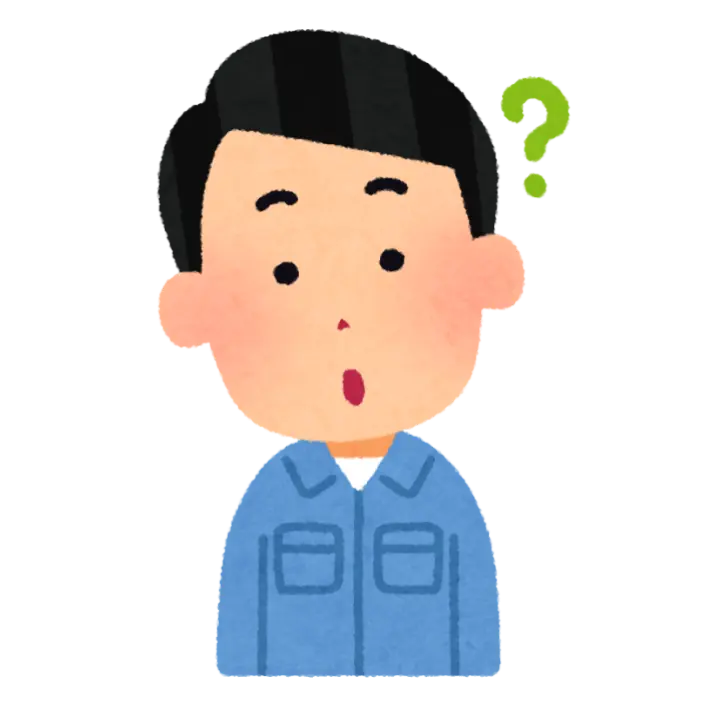
ファンが止まるだけなら危険じゃない気もしますが…

それが大きな誤解だ。止まったまま通電し続けると、モーター内部で異常発熱が起きて、最悪の場合は「焼損」や「火災」に発展する。『止まる』は、それら重大トラブルの最初の警告なんです。
「回らない」「音がする」は即点検のサイン → 放置は危険。
手で回るかどうかで大まかな原因がわかる → スムーズなら電気系、重いなら機械系の不具合。
焦げ臭さや異常発熱は最終警告 → すぐに電源を切り、交換対応を。
💡FAQ
Q1. 電気部品が動かないとき、まず何を確認すればいい?
A.まず「電源電圧が正常か」をテスターで確認しましょう。
電圧が正常でも動かない場合は、接続不良・断線・内部ショートなどの可能性があります。
また、通電状態での点検は感電や短絡の危険があるため、電源を遮断してから行うのが基本です。
Q2. 接触不良と断線はどう見分けるの?
A.接触不良は「たまに動く」「叩くと動く」など不安定動作が特徴。
断線は「全く動かない」「抵抗∞(無限大)」が特徴です。
テスターで導通を測ると、断線かどうかをすぐ判断できます。
Q3. 故障かどうか迷ったら、どうすればいい?
A.同じ型式の正常な部品と入れ替えてみるのが最も確実です。
それで動作が戻れば、元の部品が故障確定。動かなければ周辺配線や電源系を疑いましょう。
Q4. 応急処置で使い続けてもいい?
A.原則NGです。
応急処置はあくまで「安全を確保しながら原因を特定するための一時対応」です。
火災・感電・機器損傷のリスクがあるため、必ず新品交換を基本としましょう。
Q5. 部品の寿命ってどれくらい?
A.部品ごとに違いますが、目安としては以下のとおりです。
| 部品 | 一般寿命 | 備考 |
|---|---|---|
| パワーサプライ | 5〜10年 | 電解コンデンサ劣化 |
| 押しボタン/スイッチ | 10万〜100万回 | 接点摩耗で不良 |
| リレー | 約10万〜50万回 | コイル・接点劣化 |
| ファン | 約2〜5年 | 軸受摩耗・ホコリ詰まり |
| 光電管装置 | 約5年 | 発光、受光素子劣化寿命 |
Q6. 交換部品はメーカー純正じゃないとダメ?
A.原則純正部品推奨です。
同等品でも電圧・電流・接点構造などが微妙に異なる場合があり、
誤使用で別の故障や誤動作を引き起こす可能性があります。
Q7. 故障しにくくするコツは?
A.定期清掃、接点グリス、防湿対策、回転・接触系の早め交換、盤内温度管理。
日常点検で「音・匂い・熱」の違和感に注意。
- 定期的な清掃(ほこり・油分除去)
- 接点グリスや防湿対策
- ファンやリレーなど「回転・接触系」は早めの交換
- 盤内温度の上昇を防ぐ
日常点検と「音・匂い・熱」の違和感に気づくことが最大の予防策です。
まとめ
- 動作が鈍い
- 音や匂いに違和感
- 温度上昇や振動
このような小さな変化を見逃さないことで、
本格的な停止トラブルを未然に防ぐことができます。

「壊れてから直す」より「おかしいと感じたら確認する」
これが、ベテランとの一番の違いです。
テスターで測る癖をつけるだけで、
故障を“予測”できるようになります。

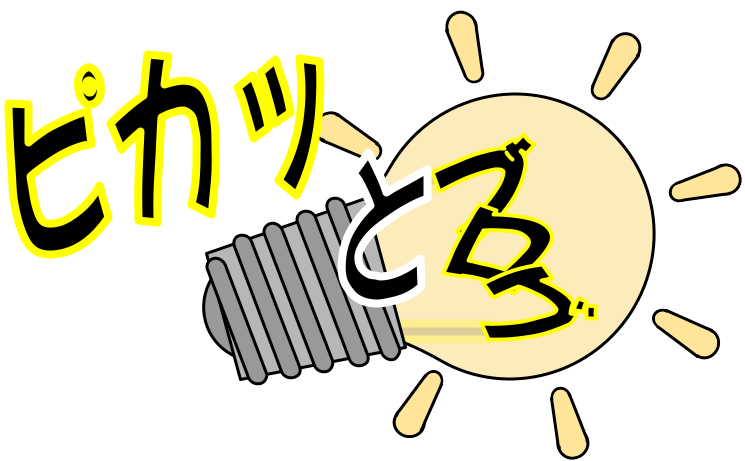
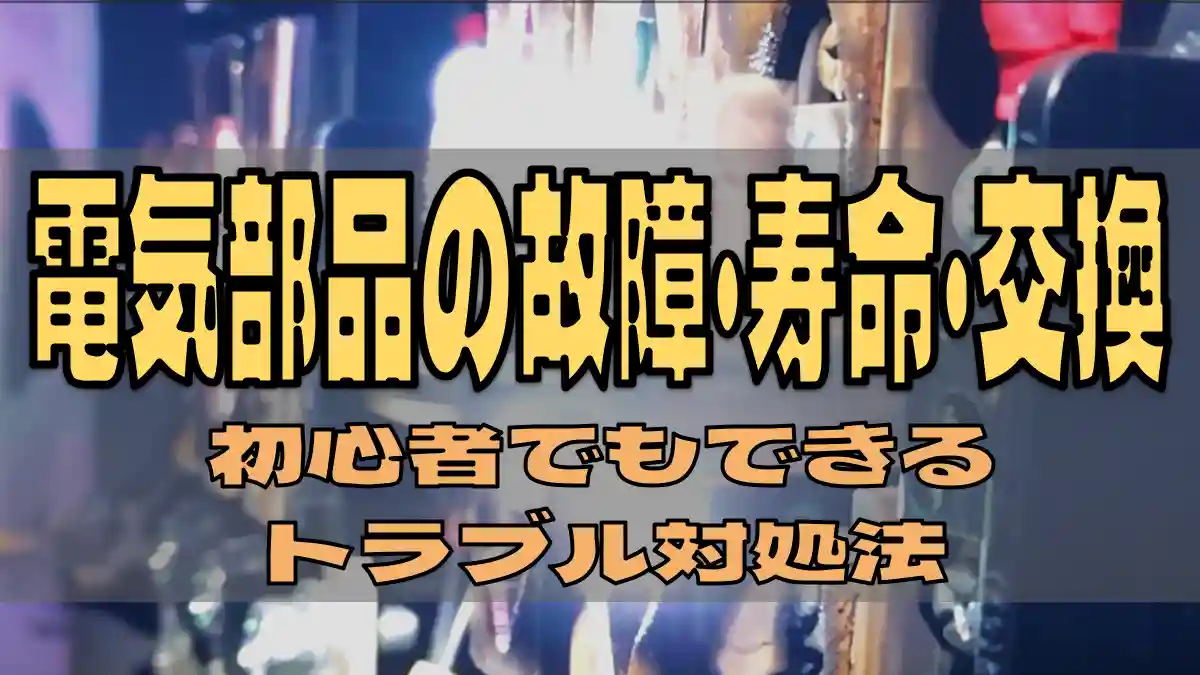
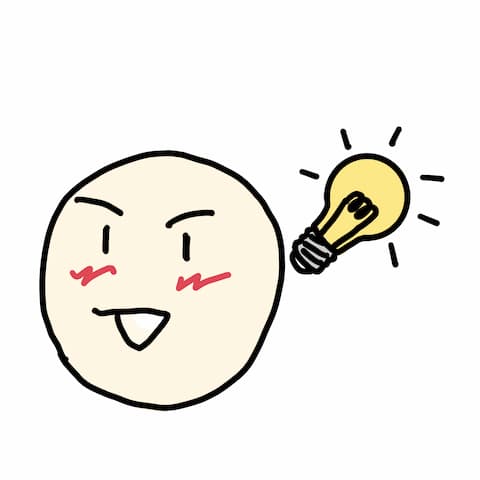
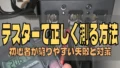

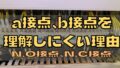
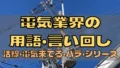

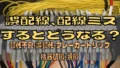
コメント